相模線複線化double track
相模線について 大規模プロジェクトのページに戻る
相模線は茅ケ崎駅〜橋本駅間を相模川に沿うようにして走る電車です。およそ60分ぐらいで橋本から茅ケ崎に行くことが出来ます。この相模線の大きな特徴は単線で、電車がボタンで開閉するところです。車窓からはのどかな相模川周辺の田園風景が見られ、ぶらり途中下車の旅にもたびたび登場します。
そんなのどかな相模線ですが、通勤時間になると、電車の待ち合わせが多く、普段よりも時間がかかります。上溝から橋本まで待ち合わせがなければ、6分で行けるところが、ひどいケースになると13分もかかります。さらに、混雑も単線ながら激しいです。
また、ここ10年で南区の駅(原当麻、下溝、相武台下)の利用者は30%増加しました。これからますます混雑が予想されます。

そんなのどかな相模線ですが、通勤時間になると、電車の待ち合わせが多く、普段よりも時間がかかります。上溝から橋本まで待ち合わせがなければ、6分で行けるところが、ひどいケースになると13分もかかります。さらに、混雑も単線ながら激しいです。
また、ここ10年で南区の駅(原当麻、下溝、相武台下)の利用者は30%増加しました。これからますます混雑が予想されます。

上溝駅での行違いを
相模線の駅の中で香川、宮山、門沢橋、厚木、入谷、下溝、上溝の7つの駅は行違いになっていません。行違いとは上りと下りの電車が行き違って停車できる駅のことです。
行違い駅を設置することで、ダイヤに余裕ができ、時間の短縮にもつながります。相模線は利用者が増加している路線です。これからも、相鉄線が都心直通になることなど、さらなる利用者増が予想されます。このため、行違い駅の設置は行う必要があります。
上溝は2001年に駅が高架化されましたが、地元の要望に反し、行違い駅は設置されませんでした。現在、行違い駅の話も出ていますが、相模原市が政令指定都市になったため、県と市の交渉が今までとは違う形になります。
しかし、利用者からしてみれば、そんなのは関係ありません。利用者が増えているにもかかわらず、行違い駅を設置しないのは、おかしな話です。また、上溝までの小田急線延伸を計画しているのに、行違い駅を設置しなかったことは小田急線延伸についてやる気がないと考えざるを得ません。
 上溝駅
上溝駅
行違い駅を設置することで、ダイヤに余裕ができ、時間の短縮にもつながります。相模線は利用者が増加している路線です。これからも、相鉄線が都心直通になることなど、さらなる利用者増が予想されます。このため、行違い駅の設置は行う必要があります。
上溝は2001年に駅が高架化されましたが、地元の要望に反し、行違い駅は設置されませんでした。現在、行違い駅の話も出ていますが、相模原市が政令指定都市になったため、県と市の交渉が今までとは違う形になります。
しかし、利用者からしてみれば、そんなのは関係ありません。利用者が増えているにもかかわらず、行違い駅を設置しないのは、おかしな話です。また、上溝までの小田急線延伸を計画しているのに、行違い駅を設置しなかったことは小田急線延伸についてやる気がないと考えざるを得ません。
 上溝駅
上溝駅相鉄線との乗り入れを
JR相模線と相模鉄道(相鉄線)は紛らわしい路線として有名です。相模線は橋本〜茅ヶ崎間を相模川と並行するように南北に走る路線で、相鉄本線は海老名〜横浜間を走る路線です。もともと、JR相模線は相模鉄道のもので、1921年に相模川の砂利を運ぶ目的で開業しました。戦時中である1944年に相模線は国策により、国有化されました。これは中央線と東海道線を結ぶバイバス線として必要な路線だったからです。(相鉄線の歴史より)
海老名〜横浜間の路線はもともと神中鉄道のものでしたが、1941年相模鉄道が吸収合併しました。そのため、紛らわしい路線が誕生しました。
相模線は赤字路線ではありましたが、工場があることなどを考慮し、そのまま維持されていました。国鉄民営化の際に、相模鉄道に変換するという話がありましたが、人事面で折り合いがつかず、話が流れたそうです。民営化後は主に周辺の通勤客、通学客が利用するようになり、今日に至ります。
相模鉄道はかしわ台から厚木駅間を走る相鉄厚木線という路線を持っており、相模線の厚木駅を車両基地として利用しています。路線は違いますが、並行して走っている区間(海老名駅〜厚木駅)がほとんどです。
この路線をうまく活用できれば、乗り入れはそう難しい話ではありません。
車両の違いにより、駅舎の改修をする必要がありますが、規模の大きな駅に限定して行うことでコストと快速ができることで利便性が高まります。山形新幹線の例があるように、新幹線ですら単線の区間が走っている場所があるので、技術的には難しくありません。
1.JPG) 単線区間を走る山形新幹線(かみのやま駅)
単線区間を走る山形新幹線(かみのやま駅)
海老名〜横浜間の路線はもともと神中鉄道のものでしたが、1941年相模鉄道が吸収合併しました。そのため、紛らわしい路線が誕生しました。
相模線は赤字路線ではありましたが、工場があることなどを考慮し、そのまま維持されていました。国鉄民営化の際に、相模鉄道に変換するという話がありましたが、人事面で折り合いがつかず、話が流れたそうです。民営化後は主に周辺の通勤客、通学客が利用するようになり、今日に至ります。
相模鉄道はかしわ台から厚木駅間を走る相鉄厚木線という路線を持っており、相模線の厚木駅を車両基地として利用しています。路線は違いますが、並行して走っている区間(海老名駅〜厚木駅)がほとんどです。
この路線をうまく活用できれば、乗り入れはそう難しい話ではありません。
車両の違いにより、駅舎の改修をする必要がありますが、規模の大きな駅に限定して行うことでコストと快速ができることで利便性が高まります。山形新幹線の例があるように、新幹線ですら単線の区間が走っている場所があるので、技術的には難しくありません。
相模線複線化の検討を
相模線は国鉄時代は赤字路線でした。しかし、沿線の人口が増加したため、経営は比較的よくなりました。その中で、相模線の複線化が望まれるようになりました。
特に相模線の複線化は相模線複線化等促進期成同盟会が結成され、神奈川県知事、茅ヶ崎市長、相模原市長、海老名市長、座間市長、寒川町長、相模原商工会議所会頭、茅ヶ崎商工会議所会頭、海老名商工会議所会頭、座間市商工会会長及び寒川町商工会会長によって組織され、相模線沿線すべての地域のトップが入っています。
同盟会のホームページhttp://www.go-go-sagamisen.ecweb.jp
また、相模線と接続している路線はほとんどが都心へアクセス可能になります。海老名駅をターミナル駅として持つ、相鉄線はJRと東急の乗り入れよって、都心へのダイレクトなアクセスがもうすぐ実現します。http://www.sotetsu.co.jp/train/into_tokyo/index.html
相模線を利用している人にとっては都心へのアクセスの選択肢が増え、利便性が向上します。さらに、相模線の倉見駅では新幹線の新駅の誘致運動もあります。このように、相模線は大きな可能性を秘めています。
相模線が複線化されることで、通勤通学時間の短縮、本数の増加につながります。相模原市にとっては、商圏が広がり、県央地域の人が橋本で買い物をするということも考えられます。また、橋本にリニア駅を設置することが出来たら、複線化の動きは一挙に進むと考えられます。
しかし、JR東日本は難色を示しています。理由は多額の費用が掛かるためです。それでも、周辺人口の増加、商圏の拡大、都心へのアクセスの選択肢が増えることを考慮すると費用対効果はあると思います。


特に相模線の複線化は相模線複線化等促進期成同盟会が結成され、神奈川県知事、茅ヶ崎市長、相模原市長、海老名市長、座間市長、寒川町長、相模原商工会議所会頭、茅ヶ崎商工会議所会頭、海老名商工会議所会頭、座間市商工会会長及び寒川町商工会会長によって組織され、相模線沿線すべての地域のトップが入っています。
同盟会のホームページhttp://www.go-go-sagamisen.ecweb.jp
また、相模線と接続している路線はほとんどが都心へアクセス可能になります。海老名駅をターミナル駅として持つ、相鉄線はJRと東急の乗り入れよって、都心へのダイレクトなアクセスがもうすぐ実現します。http://www.sotetsu.co.jp/train/into_tokyo/index.html
相模線を利用している人にとっては都心へのアクセスの選択肢が増え、利便性が向上します。さらに、相模線の倉見駅では新幹線の新駅の誘致運動もあります。このように、相模線は大きな可能性を秘めています。
相模線が複線化されることで、通勤通学時間の短縮、本数の増加につながります。相模原市にとっては、商圏が広がり、県央地域の人が橋本で買い物をするということも考えられます。また、橋本にリニア駅を設置することが出来たら、複線化の動きは一挙に進むと考えられます。
しかし、JR東日本は難色を示しています。理由は多額の費用が掛かるためです。それでも、周辺人口の増加、商圏の拡大、都心へのアクセスの選択肢が増えることを考慮すると費用対効果はあると思います。

@masakisekido からのツイート
| 相模原のイベント情報 | |
 2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) |
| 新着情報 | |
 |
|
| ・横浜線の地下化 |
| 東日本大震災関連 |
 |
| 未来思考(会の政策) |
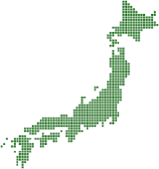 |
| お問い合わせなど |
 |
相模原の未来を考える会
電話 042−851-3715
(みないこう)