さがみ散歩〜相模湖編〜sagamiko
三歩目 〜小原宿(相模湖地域)〜
小原宿。
この本陣は生活の匂いがしていい。台所にある囲炉裏の近くに今は使われていないが、旧型の換気扇があり、囲炉裏の上にはいい煤竹があった。また、居間にも囲炉裏があり、天井がすすで黒くなっていた。トイレも汲み取り式で、「落ちたら大変」という注意書きもあった。二階は養蚕をする場になっていたらしく、昔の農具などが飾られていた。養蚕は近代日本にとって重要な産業だった。明治時代日本は貧しい国であった。その国が稼ぐために生糸(シルク)を輸出した。その生糸を出すのが、蚕(かいこ)という虫だった。蚕はクワの葉を好むので、桑畑があちらこちらにできた。屋根裏部屋に蚕を飼う家が多く、蚕の葉をむしる音で眠れないほどだったという話を祖母から聞いたことがある。
庭も本陣だけあって立派だった。左手に大きな石をそのままくり抜いたような灯篭があり、灯篭の奥には竹藪がある。右手には池があり、その奥が傾斜を利用して木が植わっている。池には水が張られていなかったが、手入れがよくされていた。全体としては武家好みの庭といったところだろうか。
駐車場には資料館というか休憩所のようなものがあったので、寄ってみた。初めに、係の方が甲州街道の小原宿について詳しく説明をしてくださった。以前から私は近藤勇が甲州街道をどのように通ったのか気になっていた。係の方はそのことについても、独自に調べてられていたらしく、丁寧に説明してくださり、個人的に集めた資料、書き留めたノートをわざわざ見せてくれた。文化、歴史というのは一人の人物が作るのではなく、いろいろな人たちが作り上げ、語り継いでいかなければできないものだと実感した。この資料館は一年前までは教育委員会の管轄になっていたが、今は経済観光課の管轄下に置かれている。そのため、以前よりも資料の展示数が少なくなり、休憩場所としての役割が大きくなった。私はそのことを疑問に思ったが、係の方が上で決めたことだからと言われた。この言葉の中に街道を生きる人々の知恵が隠れていたように思えた。
 神奈川で唯一現存する小原本陣
神奈川で唯一現存する小原本陣@masakisekido からのツイート
| 相模原のイベント情報 | |
 6月29日(日) ・さがみはら環境まつり |
| 新着情報 | |
 |
|
・災害廃棄物の進捗状況 |
| 東日本大震災関連 |
 |
| 未来思考(会の政策) |
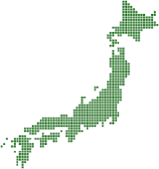 |
| さがみ散歩 |
 |
| 代表情報 |
3.jpg) |
| お問い合わせなど |
 |
相模原の未来を考える会
電話 042−851-3715
(みないこう)